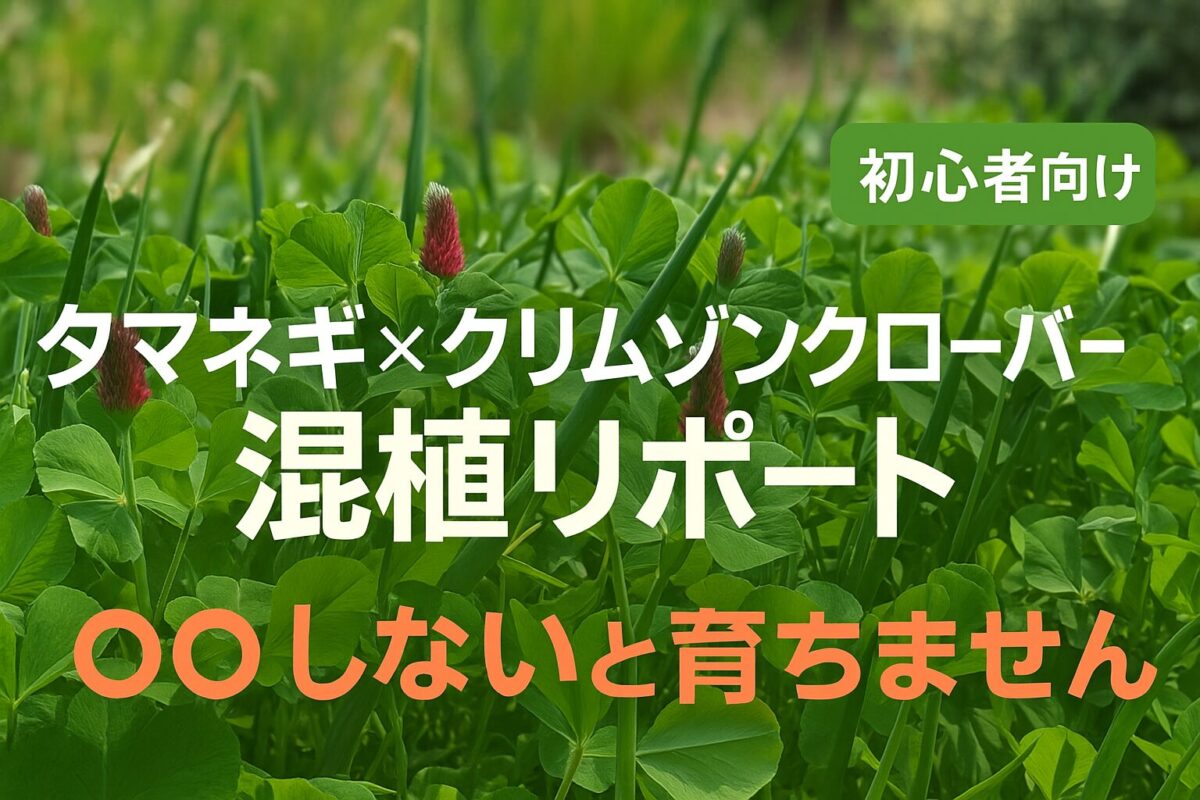はじめに
コンパニオンプランツとして人気のクリムゾンクローバーとタマネギを混植して育ててみました。
実際にやってみてわかったのは、霜よけとしての効果を期待するならもっと早く種をまく必要があるということ。
さらに、春にはクリムゾンクローバーが想像以上に大きく育ちすぎてしまい、タマネギの日当たりをさえぎる場面も。
そこで必要になったのが、こまめな管理と切り戻しでした。
本記事では、初心者の方にもわかりやすく、実際の栽培記録を通して、「うまくいったこと・うまくいかなかったこと」の両方を丁寧に紹介しています。
コンパニオンプランツに挑戦したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
合わせて読んでもらいたい記事

混植による効能
まず、混植による効能をおさらいしておきましょう。
生育促進
クリムゾンクローバーはマメ科のため、根につく根粒菌によって空気中の窒素を固定し、土を肥大にしてくれます。
生育促進
クリムゾンクローバーの柔らかい葉には、アブラムシが付きやすいが、しばらくするとテントウムシなど益虫のすみかになります。
テントウムシの影響でネギアブラムシを抑制します。
その他効能
クリムゾンクローバーにより、霜でタマネギが浮き上がるのを防いでくれます。
3月にクリムゾンクローバーが急激に成長するため、他の雑草が生えるのを防ぐ効果があります。
リポート
2024年9月21日 タマネギ種まき
タマネギは、収穫してから年末くらいまでゆっくり消費したいので、中生のO・K黄(タキイ交配)をチョイス。

畑には週末しか行けず、水やりができずに芽が出ないことがあるため、連結ポットを使って育苗してから植え付けることにしました。

2024年11月2日 タマネギ定植 クリムゾンクローバー種まき
今年は タマネギとクリムゾンクローバーを混植した場合と、タマネギのみで育てた場合を比較するため2畝に分けました。
左側が混栽で、右側がタマネギのみをうえつけています。

タマネギの株間は15cm間隔で定植。
クリムゾンクローバーはこのタイミングで種を蒔き、土が乾かないようにもみ殻でマルチングをしました。
2024年11月17日
クリムゾンクローバーが芽を出し始めました。

2024年12月16日
冬が本番。気温も10℃が以下になり、外に出るのがおっくうな季節になりました。

この時期になると、ほとんど成長はしなくなります。
霜でタマネギが浮き上がるのをクリムゾンクローバーで防止する予定でしたが、小さすぎてその役目は果たせそうにありません。
霜対策で植えるなら、9月から育て始める必要がありそうです。
この時期は追肥の時期になります。
コンパニオンプランツの野菜づくり(著者:木嶋利男さん)の中で、このコンパニオンプランツの追肥についてこのように述べられています。
”あまり肥沃(ひよく)でない畑の場合は、12月中旬~下旬に1回、2月下旬に1回、米ぬかぼかし肥を施し、表土とかき混ぜ、なじませる。少量追肥する。”
筆者の畑は、毎年野菜づくりをしているので、追肥をおこなわず、クリムゾンクローバーの根粒菌の影響を観察することにしました。
2025年2月15日
畑の様子ですが、白くパラパラと見えるのがタマゴの殻。カルシウムを補給するため水洗いして砕いたタマゴの殻を与えるようにしています。

興味があればこちらもご覧ください。
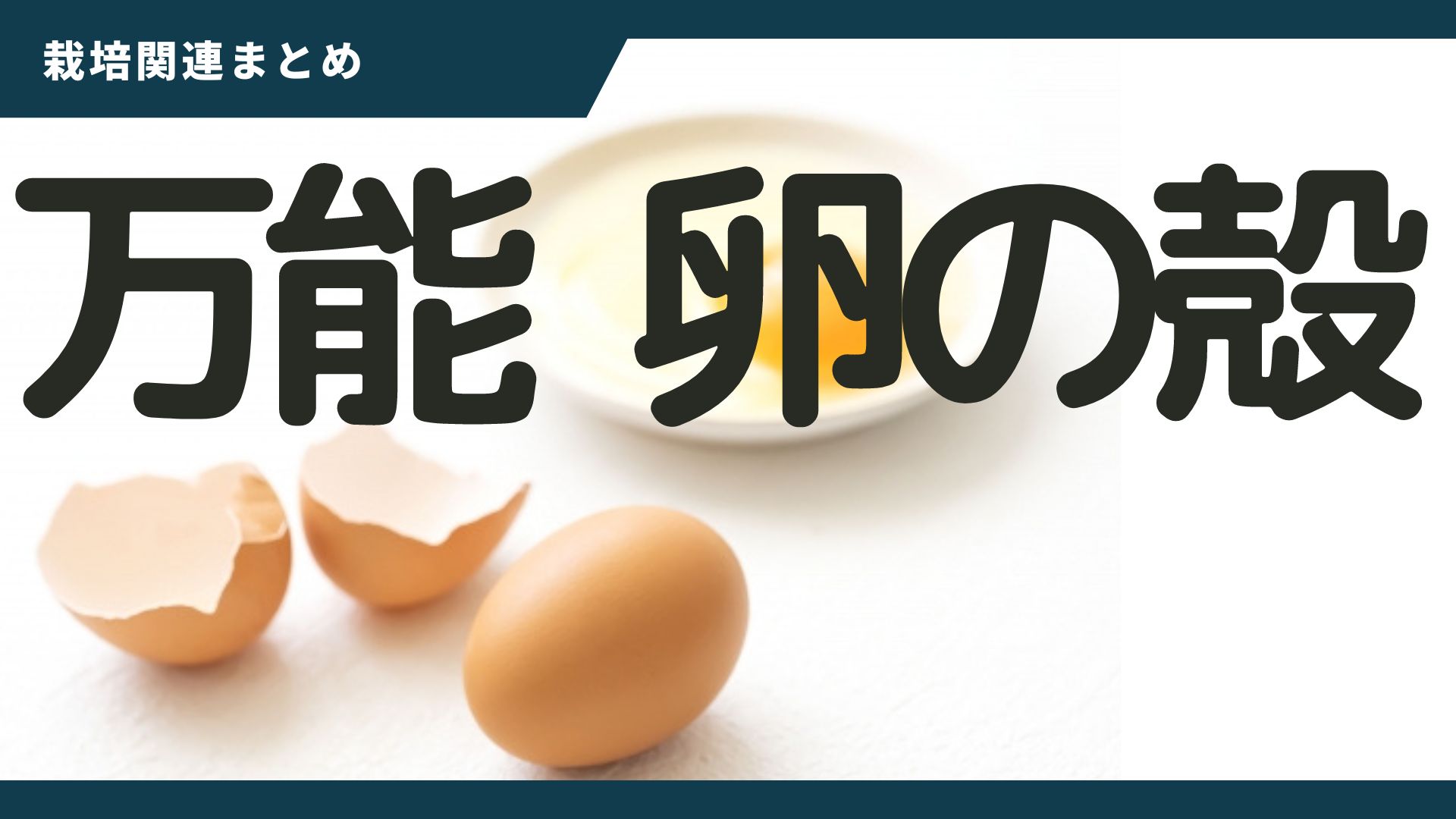
2025年3月30日
タマネギ、クリムゾンクローバー共に大きくなってきました。

タマネギのみで栽培しているものと大きさは今のところ変わりません。

2025年4月5日
クリムゾンクローバーの発芽している場所がまばらで、隙間が空いているのが気になります。

クリムゾンクローバーも順調に成長しています。

こちらは可もなく不可もなく。といったところでしょうか。

2025年4月12日
やはり、クリムゾンクローバーの隙間が気になるため、密集しているエリアを均等に振り分けて植え付けなおしました。

全体的にバランスが取れた感じがします。
2025年4月19日
!?。クリムゾンクローバーが明らかに育ちすぎです。

タマネギが隠れてしまい日光が当たらない状態に。

この時期タマネギは実を太らせる大切な時期です。
光合成で炭水化物を生成し、葉から水を発散することで大地から栄養を吸い上げるためです。
タマネギの葉が露出するようにするため、クリムゾンクローバーを株元5cmほど残して刈り取ることにしました。
刈り取った葉や茎は、草マルチとしてその場に敷きます。
2025年4月26日
タマネギの先端が少し枯れ、緑が薄い状態に。

大事な時期に光合成ができなかったのが原因だと思われます。
このままだと病気になる恐れがあるので、写真撮影後に、全体に有機石灰を振りかけました。
こちらは順調に育っているので手は入れません。

2025年5月5日
クリムゾンクローバーが花を咲かせようとするため、根を残した状態ですべて刈り取り土に敷きました。

こちらは、相変わらず手をかけません。

2025年5月18日
手前側は実が大きくなってきましたが、奥側はミニトマト位のサイズで、葉も細いまま。

クリムゾンクローバーで隠れてしまった部分は再生しない状態です。
タマネギ単体で育てている方は順調です。

2025年5月24日
奥側が育たないまま、6割ほど葉が倒れてきました。

手前側はまだ倒れていないため、収穫は次週としました。

2025年6月1日
いよいよ収穫です。
クリムゾンクローバーと育てたものは、玉が大きく育っているのは1/4くらいで、残りはゴルフビールほどの大きさでした。

単独で植えている方は、玉が大きく育ちました。

会員数5万人突破
昔を思い出して模型をつくろう!!
まとめ
今回の栽培を通して、タマネギとクリムゾンクローバーの混植には大きな可能性があると感じました。
特に、生育促進や病害虫の抑制、霜よけ・雑草防止といった効果は、理論的にも現場感覚としても納得できる部分があります。
- 霜対策としては、播種が遅すぎて効果を発揮できなかった
- 春先の旺盛な成長でタマネギに日光が届かなくなり、生育が阻害された
- 密度の偏りによる不均一な育ち方も要注意ポイント
など、播種のタイミングとその後の管理(切り戻しや間引き)が不十分だと、むしろ逆効果になることも痛感しました。
特に春の成長期には、タマネギの葉にしっかり日光が届くようにクリムゾンクローバーを早めに刈り取ることが重要です。
とはいえ、栽培後半にはクリムゾンクローバーが草マルチとして機能し緑肥になることやなど、良い側面も見られました。
また、タマネギが虫の被害を受けなかったのは、クリムゾンクローバーが益虫を呼び寄せてくれたからかもしれません。
次回は、「9月中にクリムゾンクローバーを播種する」「適宜切り戻しを行う」などの対策を取ったうえで、もう一度チャレンジしてみたいと思います。
自分の畑がある生活を送りませんか?

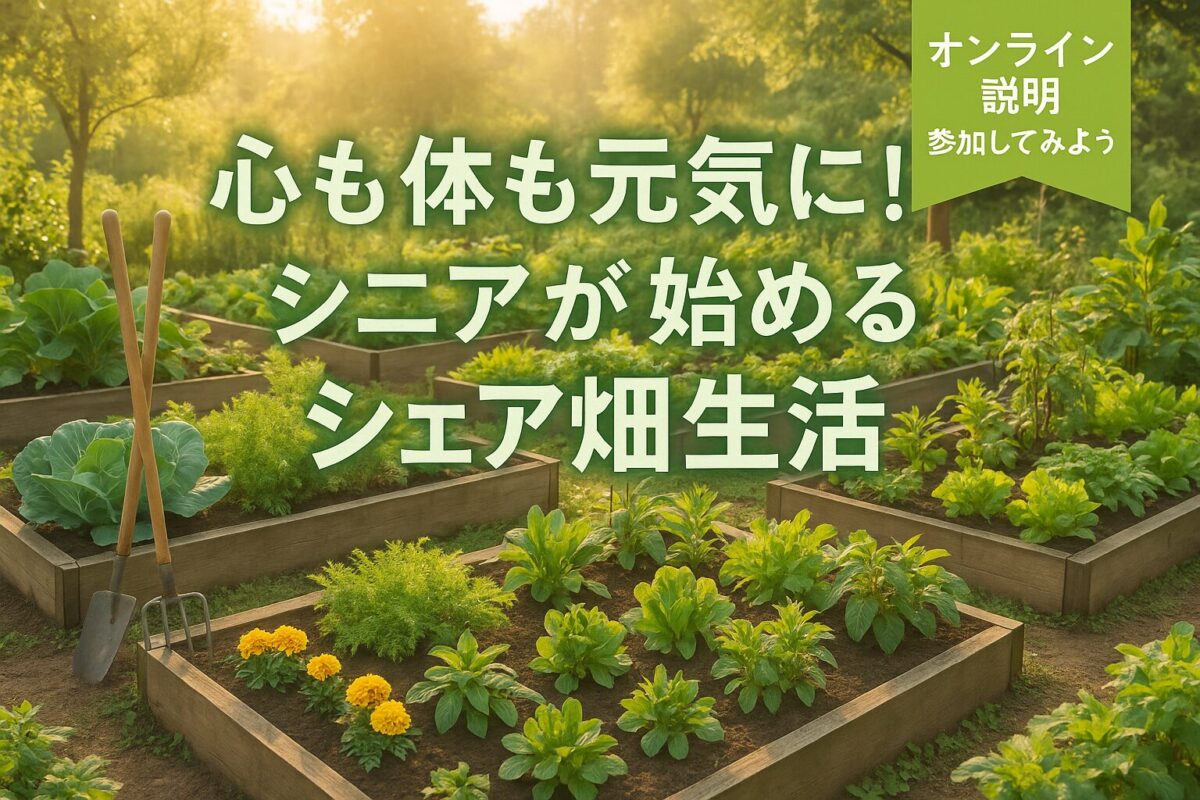
隙間時間にアンケートでお小遣い稼ぎしませんか?