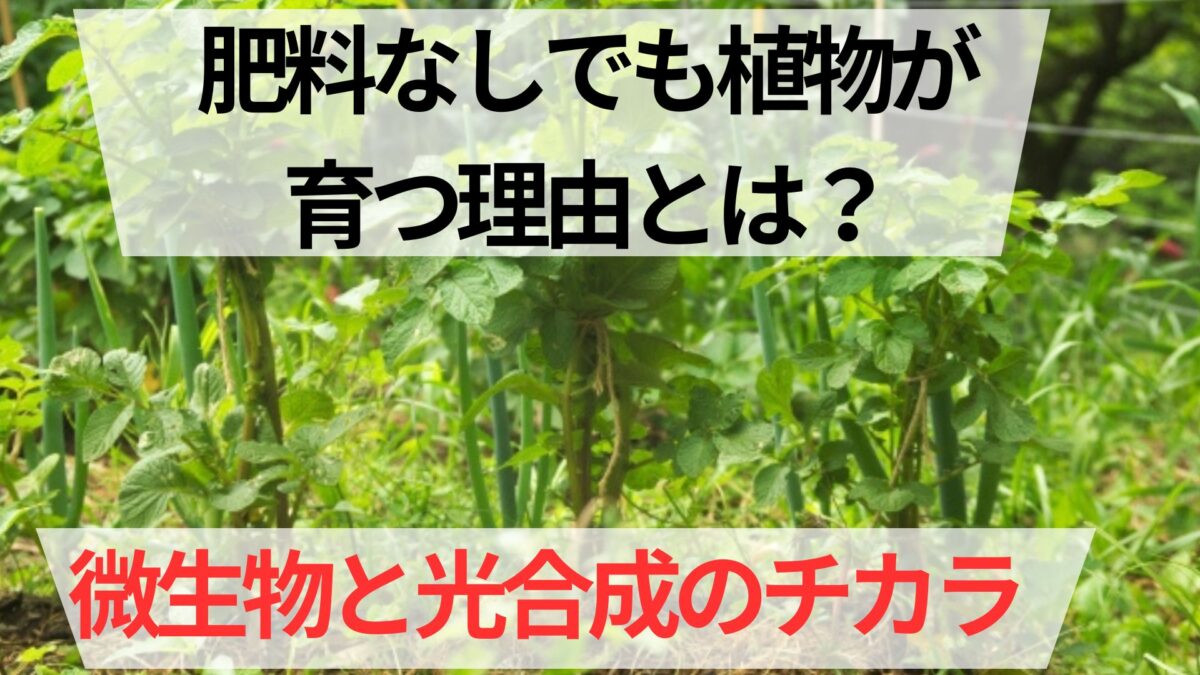はじめに
![]()
お庭や道端に生えている雑草を見て、「どうして肥料をあげていないのに元気なんだろう?」と不思議に思ったことはありませんか?
実は、その秘密は「光合成」と「微生物」の働きにあります。植物と土の中の微生物は、お互いに助け合って成長しているのです。
本記事では、光合成がどのように植物を支え、さらに微生物との共生がなぜ重要なのかを、わかりやすく解説します。
植物が元気に育つ自然の仕組みを、一緒に学んでいきましょう!
- 肥料を使わずに植物を元気に育てたい方
- 自然にやさしい農法に興味がある方
- 炭素循環農法を取り入れたいと考えている方
- 慣行農法と自然農法の違いを知りたい方
- 野菜をもっと美味しく育てたい方
- 農薬や化学肥料を減らしたいと考えている方
光合成と微生物
土手や空き地を見渡すと、肥料もまいていないのに雑草や木々が元気に育っているのを見かけます。
どうしてこんなにたくましく育つのでしょうか?
その理由は、植物がただひとりで頑張っているわけではなく、土の中の微生物が大きな助けになっているからです。
実は、植物と微生物は「共生関係」にあります。
お互いに「必要なもの」を物々交換しているのです。
では、植物が微生物に何を与え、微生物が植物に何を返しているのでしょうか?
その話の前に、まず植物の基本的な働きについて見てみましょう。
植物は「生産者」と呼ばれています。なぜそう呼ばれるのでしょうか?
それは、植物が「光合成」という、自然の中でとても大切な働きをしているからです。
光合成とは、太陽の光を浴びながら、空気中の二酸化炭素(CO₂)を吸い、水とともに反応させて酸素(O₂)を放出しながら、炭水化物(糖)を作ることです。
炭水化物とは、エネルギーの元になる栄養素のひとつで、生き物が活動するために欠かせないものです。
化学式で表すと、光合成は次のようになります。
6CO2+12H2O = C6H12O6+6H2O+6O2
二酸化炭素 6個 + 水 12個 →
炭水化物 + 水 6個 + 酸素 6個
つまり、植物はただ酸素を出しているだけでなく、自分たちのエネルギー源となる糖をつくっているのです。これが、植物が「生産者」と呼ばれる理由なのです。
さて、ここからが本題です。
植物が作り出す「炭水化物」は、実は自分たちのためだけに使っているわけではありません。
この糖を、植物は土の中の微生物に「おすそ分け」しているのです。
その微生物の中でも、特に植物と深い関係にあるのが「糸状菌(しじょうきん)」です。

糸状菌は好気性、つまり酸素と適度な水分を好む菌類で、森の落ち葉の裏などに白い糸のような姿で見つけることができます。
森の土には、この糸状菌が網のように張り巡らされています。
この糸状菌は、自分のネットワークを通じて、土に含まれるミネラルやリンなどの栄養素を吸収し、植物の根に届けてくれます。
それによって植物は、土の中からでは吸収しきれない栄養素を手に入れることができるのです。
そして、植物はそのお礼として、光合成で作った炭水化物(糖)を糸状菌に分け与えます。
こうして、「栄養と糖の交換」が成立し、植物と糸状菌はどちらも元気に成長していくのです。
このように、自然の中では、植物と微生物がお互いに助け合う関係を築いており、肥料がなくても植物が元気に育つ仕組みができているのです。
慣行農法と糸状菌
慣行農法とは、一般的な栽培方法です。
慣行農法では以下のことをおこないます。
- 植え付けた植物以外の植物(雑草)栄養を奪い、光合成を阻害するため抜き取る
- 土に空気を取り込むため土に刃をいれ耕して土を起こす
- 栄養が不足するため、化学肥料や有機肥料を施す。
至って普通の栽培ですが、この栽培方法には糸状菌が登場しません。なぜでしょうか?
実は、この方法で栽培すると糸状菌は育つことができなくなるのです。
植え付けた植物以外の植物(雑草)を抜き取るとどうなるか?
雑草が無くなると共生関係を築くチャンスが少なくなます。
そして、日陰が無くなり、土が丸裸に・・・。
土の湿り気が維持できなくなり、雨が降らないと乾燥して糸状菌が住めなくなってしまいます。
土を刃をいれて耕すとどうなるか?
土の中で作り上げた糸状菌にネットワークは破壊され、お日様の下にさらけ出されてしまうと土は乾燥して糸状菌は消えてしまいます。
肥料を与えると土壌はどうなるのか?
植物と糸状菌は共生関係にあると先に述べました。
植物は光合成で生成した炭水化物を。糸状菌は土の中で集めたミネラルやリンをお互いに物々交換して育っています。
そこに肥料が投入されると植物は苦労せず栄養を吸収できるようになります。
すると、植物は炭水化物を分け与える必要がなくなり、物々交換は終了します。
糸状菌も植物と一緒に活動するメリットが無くなり、次第に糸状菌は姿を消してしまいます。
糸状菌を増やすには・・・
土の中で大活躍する糸状菌ですが、次の4つの環境が整えることで増殖することができます。
- 空気(酸素):ふかふかで通気性のよい土が好き
- 水分:乾きすぎず、湿りすぎずのちょうどいい湿度
- 炭素資材:落ち葉やもみ殻、木くずなど、炭素を含む有機物がエサになります
- 気温:15~40℃くらいが活動しやすい温度帯
糸状菌は“固いもの”も分解する
炭素資材と呼ばれる有機物は、普通の細菌ではなかなか分解できません。
でも、糸状菌はじっくり時間をかけて、しっかり分解してくれる頼もしい存在です。
糸状菌が増えると、いい菌が集まる
糸状菌が増えると、それを住みかにして他の微生物も増えていきます。
たとえば──
- 植物の栄養になる窒素を空気中から取り込んでくれる菌
- 病原菌の活動を抑える抗生物質を出す菌
こんな仲間たちが土の中で働いてくれるようになります。
この素晴らしい糸状菌を増やし、炭素を循環させる農法を、「炭素循環農法」と呼びます。
慣行栽培と炭素循環農法のメリット、デメリット
それでは、慣行栽培と炭素循環農法のメリットとデメリットを見ていきましょう。
慣行栽培
メリット
農法が確立されている
雑草を抜き、耕して化学肥料や有機肥料を施す。そして植付けをしていく一般的な農法であるため、様々な書籍があり再現性がある。
大量生産できる
土壌の養分は肥料をすき込む量で調整できる。

デメリット
害虫が増える
投入した肥料の影響で、微量のアンモニアなどの腐敗ガスや、エチレンなどの老化ホルモンを植物自体から発してしまい虫を引き寄せてしまう。また、虫に対抗するための抵抗力も低くなる。
これらにより、葉が食害され光合成できる面積が減り、抗酸化物質が十分に作れなくなる。そして、蒸散量が減り水を吸い上げられなくなる。
土の微生物が少ない
土の上が裸になっているため、太陽の光を浴び土が乾燥します。すると、土の中の空間がなくなり次第に空気が少なくなっていきます。微生物が少なくなると、土の中の有機物が分解しきれず腐敗してアンモニアが発生し、害虫を呼び寄せてしまいます。
作付けするたびに耕し、肥料を投入する必要がある
土の中の微生物が乏しいため、畑の養分の分解が進まず、土の中の栄養も偏ってしまいます。土が乾燥して固くなっているため耕して土に空気を入れ、畑の外で発酵した肥料を投入します。肥料は畑の外で作る必要があるため場所も必要ですし、重い肥料を畑まで持っていく労力も必要になります。
野菜の栄養が低く味が落ちる
戦前に栽培していた野菜と比較すると、養分が半分以下になっている野菜が多数あるようです。また、味が落ちます。
自然農法(炭素循環農法)
メリット
野菜が美味しい
ビタミンやミネラル、ファイトケミカルたっぷりで、後に残る苦味、えぐみがほどんどなくなり甘くて風味豊かになります。野菜本来の味が引き立ちます。
また、自然栽培で育てた野菜は腐りにくい特徴があります。腐らず水分だけ抜けて枯れていくのです。
肥料を入れる必要がない
化学肥料や有機肥料、石灰までもが必要ありません。畑の栄養のかじ取りは微生物にまかせます。よって、財布に優しい農法と言えます。
肥料はいれませんが微生物のエサとして、育てた野菜の残骸や雑草を土に入れたり、炭素分が多い資材(落ち葉や木片)を入れることもあります。
作付けのたびに耕す必要がない
微生物が活性化している土は、空気を多く含んでいて、肥料も入れる必要がないため耕す必要がありません。逆に耕すと微生物が死んでしまいます。
虫被害が減る
植物は、細胞壁を厚くして組織を頑丈にし、さらに、虫が分解しにくい香りや抗酸化物質を放出することで自らを守ります。これにより、紫外線や病原菌からのダメージも防ぐことができます。

デメリット
土づくりに手間がかかる
炭素循環農法は、土壌で微生物を育てる発酵型の土づくりになります。
ただし、慣行農法をおこなっている土では肥料が投入されており、栄養素が邪魔して、糸状菌が育ちにくくなります。
そのため、炭素循環農法を行う際に、土壌の過剰な養分を一度抜く必要があります。
雑草処理が大変
土壌の発酵が進むと作物が育ちやすくなるため、雑草も大量に育つようになります。
全て抜き取ると土が乾燥するため、雑草でマルチングしたり、育ちすぎた雑草を刈ります。
雑草でも有用な品種は残す目利きができると土を育てやすくなります。
最後に
![]()
植物が元気に育つのは、光合成と微生物が助け合っているからです。
特に、糸状菌が植物の成長を支える大切な役割を果たしていることが分かりました。
慣行農法は、肥料を使うことで手軽に栽培できる一方で、土の微生物が減ってしまうデメリットもあります。
一方、炭素循環農法では、自然の仕組みを活かして土を育て、作物本来の美味しさや栄養価を引き出すことができます。
今回の記事を見て、少しでも自然農法を取り入れてみたいな。と思ってくれる方が少しでも増えてくれたら幸いです。
次回は、慣行農法から炭素循環農法へ移行する方法について記事にしたいと思います。
次回
最後までご覧頂きありがとうございます。
少しでも参考になってもらえると嬉しいです。
参考にした書籍
図や写真が多く、とてもわかりやすく解説されています。ぜひ、お手に取ってご覧ください。
消費を変えれば腸も健全化し土壌も地球も再生する。有機農法の可能性と根拠がが18もの文献を元に説明されています。おすすめです。